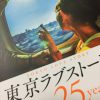【本】『脳が認める勉強法』
学ぶ前に学ぼう
大学受験であれ,資格取得であれ,大事なことは「効率的な学びの方法」を知っているかどうかである。
英語の勉強を例えにしてみよう。
海外駐在員になりたい。そのために社内の審査基準をクリアするだけの英語力を身につけなければならない…という状況で,いくつかの英会話スクールを回ったとしよう。
その際
当校で,毎日5時間,週6日通ったら3年後にはペラペラになりますよ
と言われて入学を決める人はいないだろう。
我々には学びだけに時間と労力を注ぐことはほとんどの場合許されていない。
何かをする時間と労力をやりくりしてようやく捻出している。その1日当たりで数十分,あるいは週に数時間の勉強時間を使って,目標を達成しようと思えば,それなりに「効率」がよくなければならないのである。
学ぶのは「脳」なんだから「脳」の仕組みを知ろう
そこで登場するのが「脳」についての学びである。
学ぶのは「脳」である。記憶するのも思考するのも脳の働きだ。
だから,その「脳」の仕組みを知って,その仕組みに素直に学ぶことが効率いい方法になる…実にわかりやすい発想だ。
このお正月用(?)に買っていたのが『脳が認める勉強法――「学習の科学」が明かす驚きの真実!』(ベネディクト・キャリー著/ダイヤモンド社)である。
この本では以下の四つのパートに分かれている。
Part1 脳はいかに学ぶか
→ 記憶の仕組みについての解説
Part2 記憶力を高める
→ Part1を踏まえてうまく記憶する方法を考える
Part3 解決力を高める
→ 知識を放り込むだけではなく,発想,ひらめき,創造性について考える
Part4 無意識を活用する
→ 無意識な学び,睡眠と脳の関係について
全体的には「科学的読み物」として楽しく読むことができるだろう。
目新しいことはあるのか?
もうすでによく知られていることも書かれてあるので,何もかもが目新しいというわけではない。
すでに取り入れられているものも,すでに実践されているものもあるだろう。
だから「ちまたの勉強常識は間違いだらけ!?」と帯に書かれてあるほど,全面的に衝撃的なことだらけというわけではない。
しかし,すぐに取り入れてみたくなる知見もいろいろある。その点では収穫は十分にあった。
自分の学習にも,「教える」という立場でもどちらにも有益な情報はたくさんあった。
どう活かすかは,もちろん,これからの試行錯誤ではあるけれども。
関連記事
-
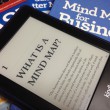
-
【Amazon】Kindleの新モデル
一度使うと手放せない 日本向けのKindleが発売されてすぐは品薄で入手困難でしたが,しばらくして
-
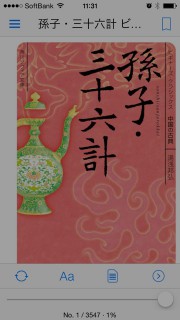
-
【本】『孫子・三十六計』
『ザ・プロフィット』の参考図書として「孫子」が出てくるので買ってみました。 『三国志演義』や『項羽
-
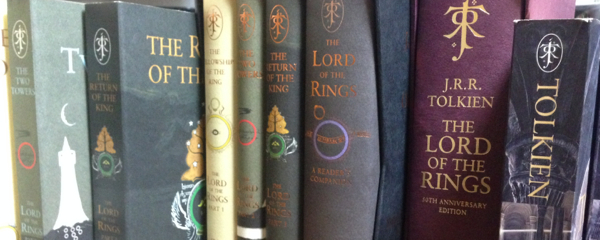
-
【本】『八つ墓村』(横溝正史)
たぁたりじゃー 『八つ墓村』は,私が小学校に入学した年,昭和52(1977)年に封切られました。
-

-
【本】『壬生義士伝』(浅田次郎著)
浅田次郎との出会い 浅田次郎の本との最初の出会いは,20年近く前に『ビジネスジャンプ』に連載されて
-
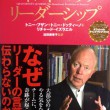
-
トニー・ブザン 優れたリーダーは「学び方」を知っている
昨年末に発売された「マインドマップ・リーダーシップ―――現場主導で組織に革命を起こす」に関連して,ダ
-
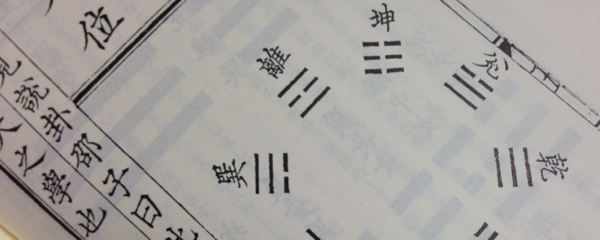
-
【易経】『易経講話』
『易経講話』(公田連太郎・明徳出版社) 昨日紹介した『易を読むために』でも紹介されてい
-
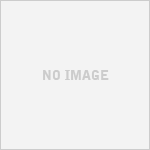
-
【本】『竜馬がゆく』
15歳の春に 司馬遼太郎の小説に初めて「はまった」のが,この『竜馬がゆく(文春文庫)』だったと記憶
-
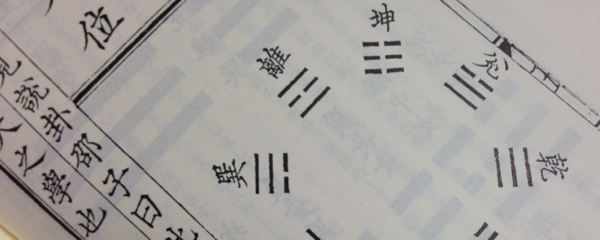
-
【本】『易経 ビギナーズ・クラシック 中国の古典』
「君子,占わず」は本当か? 高島嘉右衛門に関する本(『横浜をつくった男』『乾坤一代男』の2冊)を読
-

-
【本】『人生と陽明学』
安岡正篤活学シリーズ PHP文庫の活学シリーズの第2弾に当たるのが,この『人生と陽明学 (PHP文
-

-
【本】『世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法』
『世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法』 先日,大阪梅田の紀伊國屋書店に立ち寄ったとき
- PREV
- 【映画】『怪盗グルーの月泥棒』
- NEXT
- 【2016年】新年のテーマ 〜インプット〜